最終更新:2025/10/20
結論(最初に)
引越しや婚姻・離婚などで住所や氏名が変わったら、まず住民票の手続きを済ませ、その後にマイナンバーカードの記載変更と電子証明書の状態確認を行います。順番は住民票 → カード券面 → 電子証明書が基本です。
手続きの順番(最短ルート)
- 住民票の手続き(転入届/戸籍・婚姻関連の変更)を先に完了。
- マイナンバーカードの記載変更(氏名・住所など)。自治体の窓口で実施します。
- 電子証明書(JPKI)の確認・更新(必要に応じて再発行・暗証番号再設定)。
- 関連する保険・金融・免許など各所の住所/氏名変更も順次対応。
自治体により案内や必要書類、受付方法が異なります。事前に公式ページを確認するとスムーズです。
必要書類(目安)
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(運転免許証など。組合せは自治体案内に従います)
- 住民票・戸籍関係書類(婚姻・離婚・本籍関連の変更がある場合)
- 通知カード・運転免許証など他の氏名/住所変更が必要なもの(当日案内に従ってください)
手数料は自治体運用によります(記載変更は無料運用が多いですが、再交付を伴う場合は費用がかかることがあります)。
窓口での流れ(所要の目安)
- 窓口で「マイナンバーカード記載事項の変更」を申し出ます。
- 本人確認 → 端末でカードを読み取り → 券面の記載更新(自治体方式に従います)。
- 電子証明書の状態確認。氏名変更などの内容によっては失効→再発行や暗証番号の再設定が必要です。
- 完了票を受領。必要ならその場でマイナポータルのログイン等を試して確認します。
電子証明書と暗証番号の扱い
- 氏名変更を伴う場合、署名用電子証明書などの失効・再発行が必要になることがあります。
- 住所変更のみでも、電子証明書の状態確認が推奨です。必要に応じて更新・再発行を行います。
- 暗証番号が不明/ロックの場合は、同時に初期化→再設定ができます。暗証番号を忘れた/ロックした時
- 記載変更の途中は、一時的にログインやコンビニ交付が使えないことがあります。完了後に動作確認を。
ケース別メモ
- 引越し(市区町村をまたぐ転居)
- 転出・転入の住民票手続きを先に完了。転入先の自治体でカード記載変更と電子証明書の確認を行います。
- 婚姻で氏名が変わった
- 戸籍の変更手続き後、カードの氏名記載変更。電子証明書は内容に応じて失効→再発行が必要になる場合があります。
- 離婚で旧姓に戻す
- 戸籍変更の反映後にカードの氏名変更を実施。電子証明書の再発行と暗証番号の再設定を確認します。
- 旧姓併記をしたい
- 対応可否・記載方法は自治体案内に従います。事前に必要書類を確認してください。
やってはいけないこと
- 住民票の変更より先にカードだけ変更(順番が逆だとやり直しが発生します)。
- 暗証番号を当てずっぽうで連続入力(4桁は3回でロック→窓口初期化)。
- 記載変更が終わるまでにオンライン手続きを繰り返し試す(失敗履歴が増えるだけのことがあります)。
目次
関連記事
よくある質問
- 電子証明書は必ず更新が必要ですか?
- 内容の変更(氏名など)がある場合は、失効・再発行が必要になることがあります。窓口で確認のうえ、その場で対応できます。
- 手数料はかかりますか?
- 自治体運用により異なります。記載変更は無料運用が多いですが、再交付・再発行を伴う場合は費用がかかることがあります。
- 当日中に終わりますか?
- 記載変更と証明書の対応は当日完了が一般的です。混雑や書類不足があると再来庁になることがあります。
公式リンク
※本記事は一般向けの概要です。必要書類・手数料・受付方法は自治体により異なります。最新の案内は必ず公式ページでご確認ください。
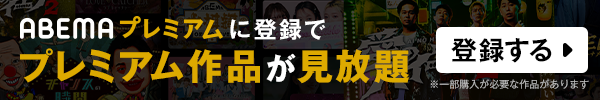
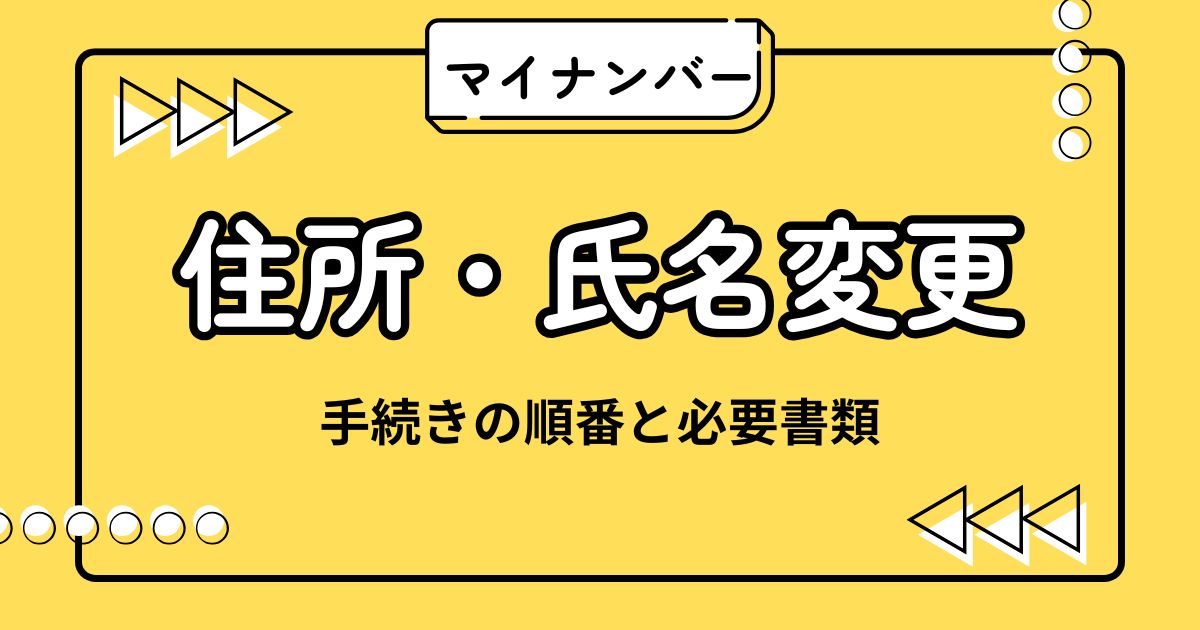
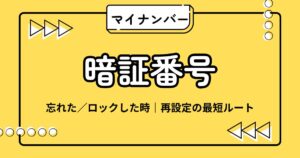
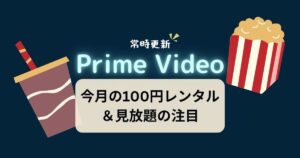



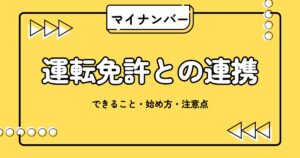
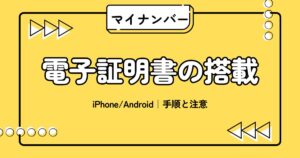
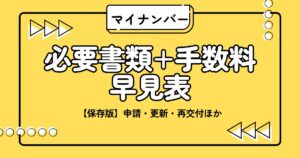
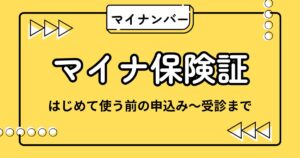
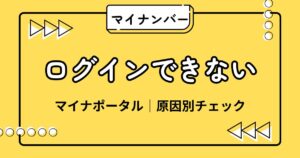

コメント