結論(最初に)
カードの更新は有効期限の約3か月前から案内が届くのが目安です。流れはオンライン等で申請 → 交付通知書が届く → 来庁で受取り。受取り時に暗証番号(4桁×2/署名用6〜16桁)を設定・確認します。
いつからできる?(タイミングの目安)
- 案内が来たら着手(多くは期限の約3か月前)。
- 更新申請自体は早めでも問題ありません。受取りは自治体の準備が整い次第。
- 電子証明書は5年で先に切れることがあります(年齢に関わらず)。状態確認を忘れずに。
更新の手順(最短ルート)
- 申請 ─ 案内のQRコードや自治体ページからオンライン申請(または証明写真機/郵送)。
- 交付通知書が到着 ─ 受取り場所・持ち物・予約方法を確認。
- 来庁して受取り ─ 本人確認→カード受取→暗証番号を設定/確認。必要に応じて電子証明書の更新/再発行も同時に。
所要は窓口で10〜20分が目安(混雑・書類不備で変動)。
必要書類(目安)
- 交付通知書(はがき等)
- 本人確認書類(運転免許証など。組み合わせは自治体案内に従う)
- 顔写真(方式により不要/写真機・オンラインで済む場合あり)
- 旧カード(受取り時に返納/交換)
電子証明書は同時に確認(更新/再発行)
- ログインやコンビニ交付を使う場合は電子証明書(JPKI)の状態を確認。
- 期限切れ・失効・未搭載なら窓口で更新/再発行を同時に実施。
- 暗証番号が曖昧な場合は推測入力せず、窓口で初期化→再設定が安全。
つまずきやすい所
- 写真の規格(サイズ・背景・表情)で差し戻し。案内どおりに撮影・提出。
- 予約枠の混雑。キャンセル枠は朝に出やすいことが多い。時間帯分散が有効。
- 氏名・住所変更が未対応のまま更新へ行くと手戻り。先に住民票/戸籍→記載変更を整える。
目次
関連記事
よくある質問
- 手数料はかかりますか?
- 自治体運用によります。更新は無料運用が多いですが、再交付を伴う場合などは費用が発生します。
- 更新はオンラインだけで完結しますか?
- 申請はオンライン可ですが、受取りは来庁が必要です。
- 電子証明書は必ず同時に更新が必要?
- カード有効でも電子証明書は5年で別カウント。状態に応じて更新/再発行を行います。
- 当日、暗証番号を忘れた場合は?
- 窓口で初期化→再設定が可能です(推測入力はロックの原因)。
公式リンク
※本記事は一般向けの概要です。必要書類・手数料・予約方法・所要時間は自治体により異なります。最新の案内は必ず自治体・公式ページでご確認ください。
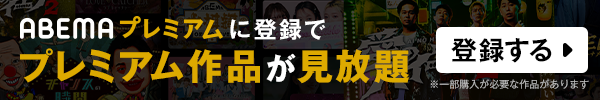
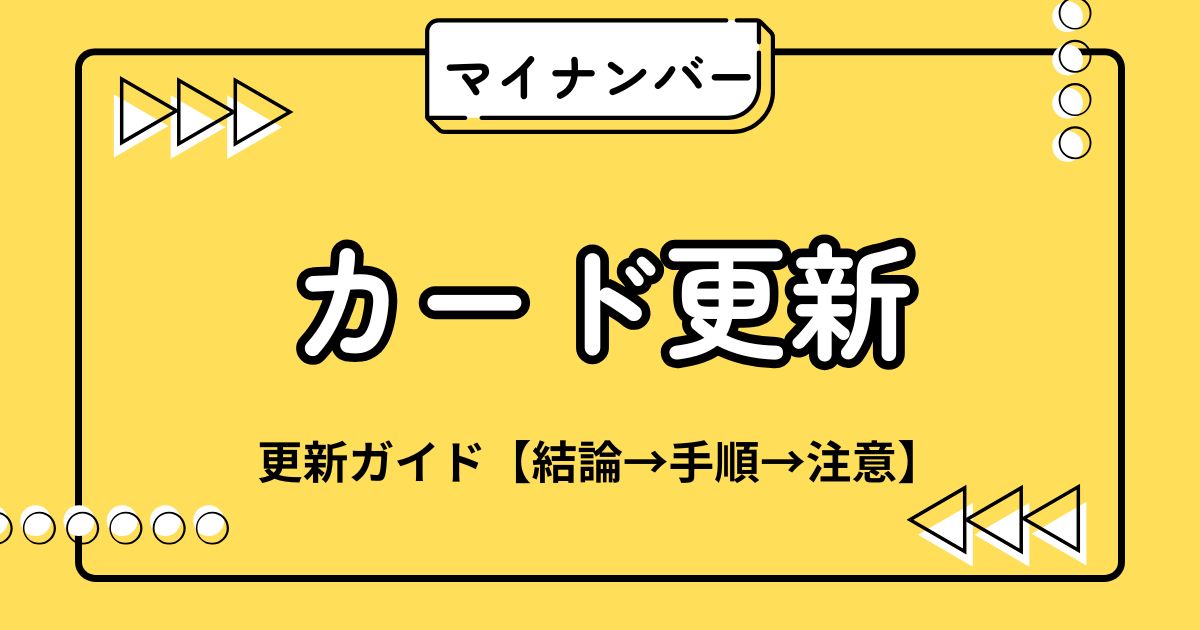
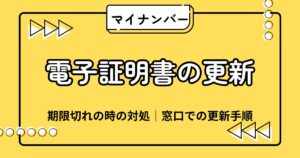



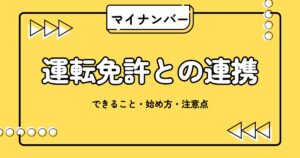
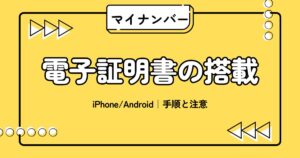
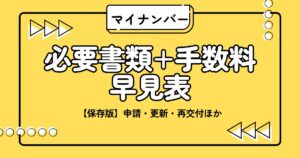
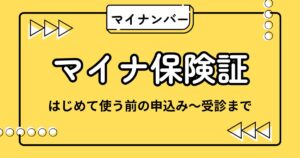
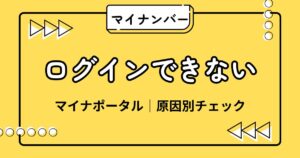

コメント